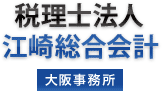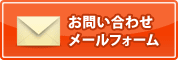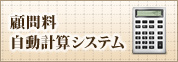相続における制限納税義務者の具体例
「制限納税義務者」をイメージしやすくするために、米メジャーリーグに行って活躍するI選手の父親が亡くなったというケースで考えてみます。
I選手は日本国籍を有していますが、渡米して既に15年以上が経過し、当然アメリカに住所を有しています。
その父親が、日本で亡くなった場合には、I選手の日本の相続税の納税義務はどうなるでしょうか。
「非居住無制限納税義務者」となり、父親の所有していた財産を相続により取得した場合にはそのすべての財産に課税されます。
被相続人が日本に住所を有している者だからです。
仮に父親がアメリカに別荘を所有しており、その別荘をI選手が相続すれば、日本の相続税が課税されます。
つまり、アメリカに住んでいる息子がアメリカに所在する父の遺産を相続し、日本の相続税を納税します。
一方で、父親も息子と一緒にアメリカに移住していたとすれば事情が変わってきます。
例えば、父親も定年後は息子と一緒にアメリカに移住しており、そのアメリカでの生活が10年を超える場合には、その父がアメリカで亡くなれば、双方が10年超の間日本に住所を有しないため、I選手は「制限納税義務者」となります。
従って、父がアメリカで所有している現預金などの財産を相続しても、日本の相続税はかかりません。
日本にまだ残っている財産のみが課税の対象となります。
以上のように、今回の改正では双方が10年超の外国住所を有することが必要となったので、以前の5年超よりも「制限納税義務者」となる条件が厳しくなりました。
実際に、相続の対策ということではなく、子どもの教育の観点や、リタイア後の余暇という面から、将来外国に移住を考えている方も顧問先のお客様のなかにはいらっしゃいます。
そういった場合には、税務上の問題が多かれ少なかれ生じますので、事前に検討しておくことが望ましいと思います。
・2017年7月11日 配信
« H29年改正:制限納税義務者||